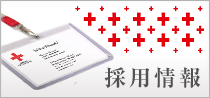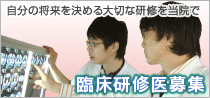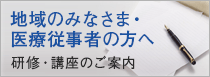⇒大動脈瘤に対する低侵襲治療(ステントグラフト治療)について
|
役職/部長
氏名/馬瀬 泰美 |
所属学会 認定医等 |
日本外科学会専門医 日本胸部外科学会認定医 日本心臓血管外科学会専門医・修練指導者 日本呼吸器外科学会 日本血管外科学会 日本集中治療医学会 医学博士 |
| 専門領域 | 心臓血管外科 |
 役職/部長
氏名/山本 直樹 |
所属学会 認定医等 |
日本外科学会専門医 日本胸部外科学会 日本心臓血管外科学会専門医・修練指導者 日本血管外科学会 日本脈管学会 日本人工臓器学会 日本循環器学会 博士(医学) 関西胸部外科学会評議員 |
| 専門領域 | 心臓血管外科 |
|
役職/医師
氏名/井上 良哉 |
所属学会 認定医等 |
日本外科学会専門医 日本血管外科学会 日本胸部外科学会 日本心臓血管外科学会専門医 胸部・腹部大動脈ステントグラフト実施医 日本DMAT隊員・統括DMAT |
| 専門領域 | 胸部外科全般 |
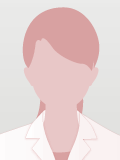 役職/医師
氏名/別所 早紀 |
所属学会 認定医等 |
日本外科学会専門医・外科学会評議員 日本胸部外科学会 日本心臓血管外科学会・U-40中部支部幹事 日本心臓血管外科専門医 |
| 専門領域 | 胸部外科全般 |
|
役職/医師
氏名/村上 理彦 |
所属学会 認定医等 |
日本外科学会専門医 日本心臓血管外科学会 日本胸部外科学会 |
| 専門領域 | 胸部外科全般 |
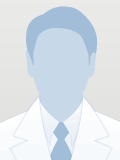 役職/嘱託医師
氏名/世古口 知丈 |
所属学会 認定医等 |
日本外科学会 日本胸部外科学会 日本血管外科学会 |
| 専門領域 | 胸部外科全般 |
一般的には胸部外科と通称されており、心臓血管外科(心疾患・大動脈疾患・末消血管疾患)及び呼吸器外科(肺・縦隔疾患)を業務としております。
手術に際しましては、循環器科・呼吸器科・放射線科・麻酔科と連携、協議のうえで総合的な治療を行うようにしております。
私たちは手術時の使用機材の縮小だけではなく、体にとっての本当の意味での低侵襲・High Qualityを追及することを目標としております。
我々が担当します診療圏は主に三重県南部地方であり、唯一の胸部外科施設としての役割を果たしております。
伊勢市及びその近郊にお住まいの方を中心に、松阪・志摩・紀州地区にいたる広範囲な地域からも受診していただいております。
心疾患では主に後天性疾患を対象としております。
狭心症や心筋梗塞に対する治療とされる冠動脈バイパス術におきましては、人工心肺を用いないオフポンプバイパス術と人工心肺を用いるオンポンプバイパス術を個々の症例に応じて選択しています。
早期の離床が可能となり、術後は約2週間での退院となっております。
近年高齢化社会に伴って増加しております大動脈弁疾患に対しましては、可能な限り生体弁を使用する人工弁置換術をおこなうことで、術後の生活の質向上を目指しております。
僧帽弁疾患に対しましては、可能な限り自己の弁を温存して形成する弁形成術を行い、術後の生活の質向上を目指しております。
弁膜症(大動脈弁や僧帽弁疾患)はなかなか自覚症状がでにくい一方、急速に悪化して心不全等に至ることがあり、早期発見・早期治療が大切です。
大動脈疾患としましてはほとんどが動脈瘤で、血管が風船の様に大きくなってくる真性動脈瘤と血管壁が裂けてしまう解離性動脈瘤があります。
どちらもその瘤径が5~5.5cmを超えてくると破裂の危険が高くなり、破裂すると突然死につながることから治療の対象となってきます。
一方、突然発症する急性大動脈解離におきましては、心臓から出てすぐの大動脈(上行大動脈)に波及する場合、約90%が発症1週間以内に破裂するとされており、緊急手術の対象となってきます。
横隔膜よりも上(胸側)に発症したものを胸部動脈瘤、下(お腹側)に発症したものを腹部動脈瘤、両方にまたがるものを胸腹部動脈瘤と分類しております。
原則耐術者(手術に耐えられる方)に対しましては、人工血管による置換術を、その他の方及び適応のある方に対しましては血管内治療(ステント治療)を行っております。
近年、動脈瘤に対するステント治療は、材料・手技の向上によってその適応が拡大されております。
全身麻酔は必要ですが、小さな創からカテーテルを挿入して動脈瘤をステントによってカバーしてしまう治療法です。
特に胸部動脈瘤では手術に比較すると低侵襲であり、適応症例を選択して試行しております。
末梢血管疾患では血管が狭窄・閉塞してくることによる血流障害から、歩行によって下肢疼痛を来たす閉塞性動脈硬化症で困り受診される方が増えてきております。
このような方に対しましては、人工血管あるいは自家静脈によるバイパス術を行う血行再建術を行い、機能回復を目指しております。
呼吸器疾患のうち、近年その罹患率・死亡率の増加が問題となっております肺癌に対しましては、胸腔鏡(カメラ)を用い、可及的筋肉を温存する小開胸手術(約5cmの切開)hybrid VATS法を取り入れることで、早期離床・疼痛軽減・美容的利点をもたらすことができております。
これにより、早期退院が可能となり、現在は術後約4~7日で元気に社会復帰していただいております。
また、良性疾患として若年者を中心に見られます自然気胸に対しましても胸腔鏡を用いた低侵襲手術を試行しており、術後約3日程度で早期の社会復帰をしていただいております。
一方、肺癌症例の中には周囲臓器(胸壁や大血管等)への浸潤をすでに伴っている場合もあり、こういった症例に対しましては呼吸器科・放射線科との連携のもと術前・後の放射線治療や科学療法と併用した上での拡大手術へも積極的に取り組んでおります。
縦隔疾患として最も多いものに、縦隔腫瘍がありますが、本疾患におきましては胸腔鏡を用いた低侵襲手術を積極的に行っております。
循環器科・呼吸器科・放射線科等との連携及び地域開業医や基幹病院との連携をますます深めることで、胸部外科関連疾患の早期発見・早期治療に努め、ますます低侵襲で質の高い治療を提供できますよう努力しております。
| 令和6年1年間の手術件数 | |||
| 心臓手術 | 87例 | 大動脈手術 | 109例※ |
| 末梢動脈手術 | 23例 | 縦隔手術 | 14例 |
| 悪性肺手術 | 65例 | その他手術 | 14例 |
| 肺手術 | 18例 | 合計 | 330例 |
※うちステント21例